学生の時は文章を作成しても、添削してくれる先生がいましたが、社会人になると、自分でチェックして完成度を高めて、完璧だ!と思うくらいにして提出することになるのではないでしょうか。就活のPR分も先生に添削してもらっていたり、友達や親に見てもらったり…などなど、そもそも「書類作成が苦手」という人の為に、「自分で自分の作成した文章をチェックするポイント」を紹介します。
読み手を意識する。誰が読むのか。どんな人が読むのか
仕事での書類作成には、必ず「読み手」がいます。読み手のその文章表現による「受け取り方」を考慮しない文章は親切ではありません。
誰が読むのか、どんな人が読むのか、ターゲットを明らかにしてからスタートしましょう。
上司が読むのか、顧客が読むのか、読み手は様々でしょう。
マニュアルのように「誰が読んでも伝わる文章」を書く場合もあります。
文章の形式は統一する。形式が整っていないと、そもそも読む気にならない。
どんなに良い文章を書いていたとしても、形式が整っていないと、「こんな基本的なことができないのか、読み手のことを考えているのか、そもそも読みにくい」と思う人がいます。
書いている自分が良くても、世の中には、「文章作成のルール」というものが存在します。
わからない場合は、ルールを調べる努力が必要です。
基本的なことがどのレベルかというと、「1、2、3」を使用していないのに、初めから「①、②、③」を使い始めるようなものです。
Ward文書で書類を作成する際は、ツールを最大限利用しましょう。箇条書きや、番号も簡単につけることができます。
MicrosoftOfficeのWardとExcelの勉強をしておくことは、社会人の基礎として有効でしょう。
もし、これからの仕事でパソコンを使う機会があるのでしたらOfficeのWardとExcelの勉強をした方が得でだと思います。
私の場合、学生の頃のレポートでWardを使用していましたが、MicrosoftOfficeの検定の勉強をして「のこんなに便利なツールがあるのか~」と初めて知ったものもあります。
ツールを使えば、ツールを使わない時よりも、「無駄に考えずに」整った形式の文章を作成することができます。
主語と述語をチェックする。主語は長すぎると読み辛い
説明文は、小説のような文章である必要がないのです。
例えば、「□□をしている〇〇は~」ではなくて「〇〇は□□をしている」とか、「□□している際〇〇は~」ではなく「〇〇が□□した際、」ということです。
私は、「が、は、も、こそ、さえ」の前の主語は長くならないように心がけています。
もし迷った時は、「英語だと大抵 It isだよな」だとか「この文章だとthatが出てきてしまうなあ」と思うようにしています。
文章は主語と述語があまりにも離れすぎていると読みにくい
英語の場合、は主語と述語は隣同士のことが多いです。
例えば、「私は○○できる」は「I cam ○○」ですね。
日本語の場合は、主語と述語の間に、形容詞や修飾語が入ります。
したがって、述語を目にするまで結局何をしたのか、どうなったのかがわかりません。
文章は多くても3行、2行目の前半くらいで終えると、「読んでる間に何の話だったか忘れない文章」になると思います。
単語の表現は途中で変えない
例えば、同じ文章の中で「絆創膏」のことを、「バンドエイド」と書いたり、「キズバン」と書いたり、「カットバン」と言ったりすると、たとえ同じものを指していたとしても読み辛くなります。
始めに絆創膏という単語を使ったのであれば、最後まで絆創膏を使いましょう。
話が複雑になればなるほど、名刺と単語の統一は大切です。
文章のチェックポイント
ビジネス文書は形式を守り、「伝えたいことを伝えるスタート時点に立てているのか」チェックしましょう。
マニュアルは、誰が読んでもわかりやすい文章、つまり、「主語と述語がはっきりしているか」のチェックを大切にしましょう。
始めは書きたいことを羅列することから始める(要素の書き出し)
始めのうちは、書きたいことを羅列して(必ず入れたい要素を抽出して)ブラッシュアップしていくと良いでしょう。
ブラッシュアップのチェックポイントを自分で決めておくことで、文章作成の時間短縮につながります。
また、ブラッシュアップを繰り返し行うと、ブラッシュアップの量自体が少なくなってきます。
できるだけ短時間で、伝わる文章、わかる文章を書けるようにするには、ポイントを押さえて、指摘があったら反省し、次で実践することが大切です。
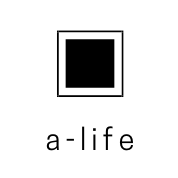
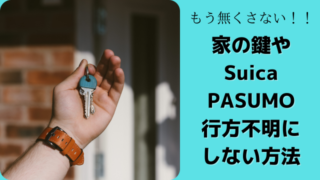



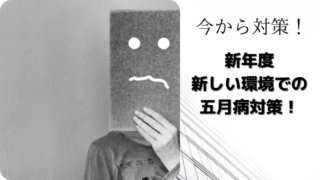
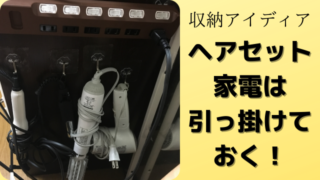




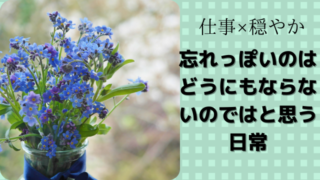
-320x180.png)
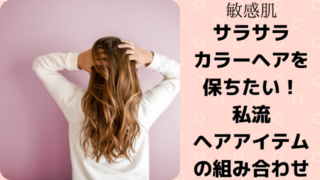


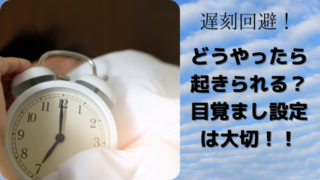




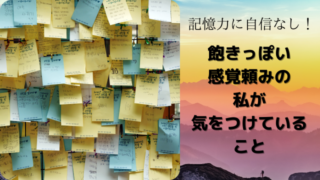


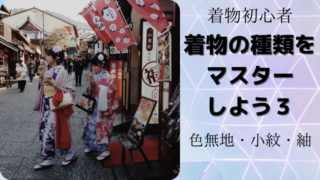
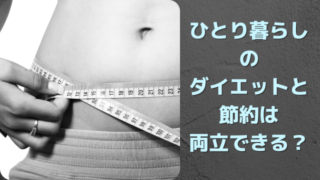


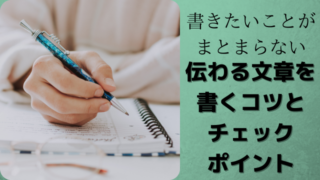











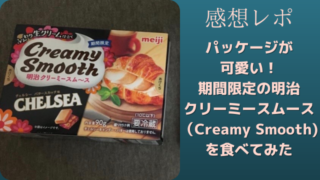
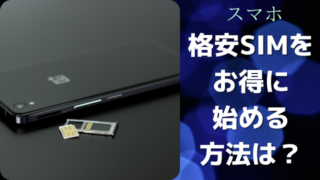
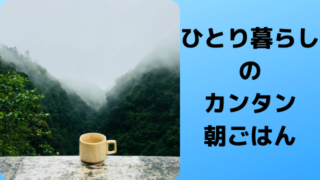
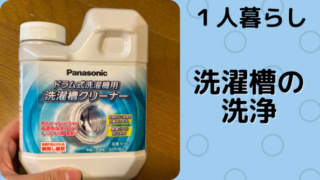


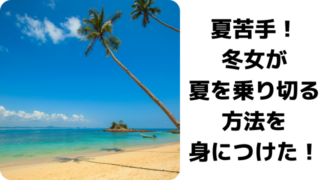
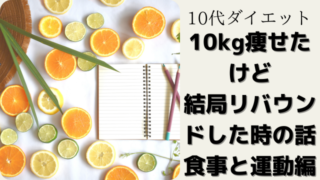

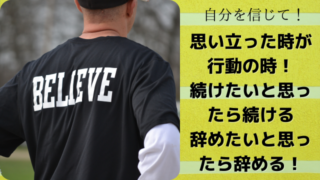

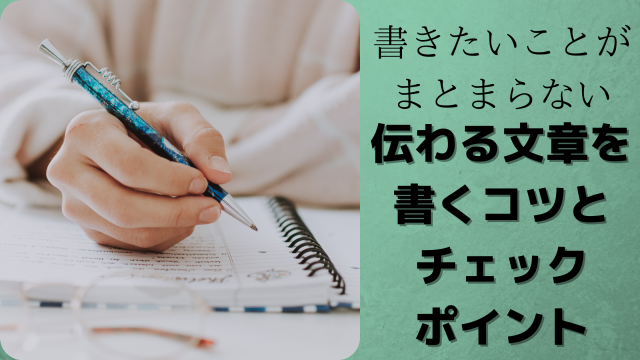

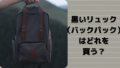
コメント